

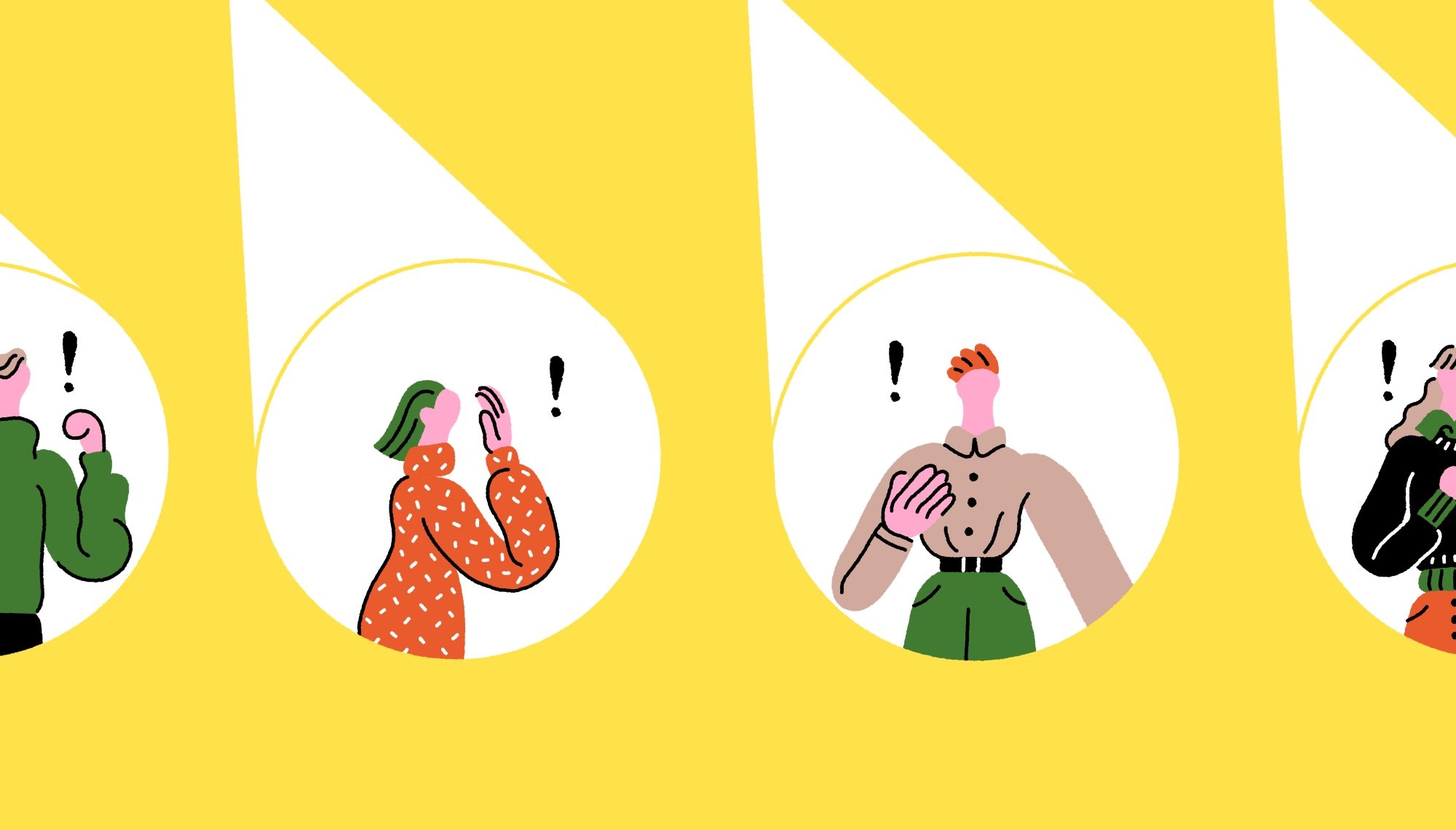
悪い点を指摘するのではなく、まずいいところを見つけて褒める。そんな場面が少しずつ増えてきました。自分自身を褒める動きが見られたり、成果や結果だけでなく「その人らしさ」が褒められたりと、「褒められる事柄」も、以前より広がってきているように思います。
では、褒め合うことが当たり前の社会に突入するために、私たちはどんな考え方を持つとよいのでしょうか。何をどう褒めるかを見つめ直すことは、これからの価値観にもつながっていくはずです。F.I.N.編集部は、時代の目利きたちとともに「褒め合う社会になっていくには?」を考えていきます。
今回お話を伺うのは、文化としての広告表現を研究する、法政大学教授の青木貞茂さん。「褒める」広告の登場は、社会の状況とどのように関係しているのでしょうか。人々を褒める広告の事例を参照しながら、広告がつくられた背景やこれからの社会に求められるメッセージなどを教えてもらいました。
(文:大芦実穂/イラスト:小泉由美)
青木貞茂さん(あおき・さだしげ)
1956年、長野県生まれ。法政大学社会学部メディア社会学科教授。専門は広告論、ブランド論。立教大学経済学部卒業後、広告会社勤務を経て同志社大学社会学部教授などを歴任。
過酷な状況を乗り越えた時に、「褒める」広告は出てくる
青木さん
広告は「これは素晴らしい価値がある」ということを伝えるために、いろんな工夫を凝らします。例えば、夏目漱石が「I love you」を「月がきれいですね」と訳したように、必ずレトリックや表現の工夫をするんですね。つまり、1番伝えたいことは「褒める」ではなく、背後に別の意味合いがあるんです。
F.I.N.編集部
例えばACジャパンの「おとなもほめよう」(2014)や、ルミネの「MERRY GOOD JOB! ほめよう。わたしたちを。」(2020)といった「褒める」という表現を使っている広告には、どんな意味合いがあったのでしょうか。
青木さん
この時の「ほめよう」は、普段頑張っている自分たちについてのある種のねぎらいの言葉であったり、勇気づけ、英語で言うとエンパワーメントですよね。コロナ禍のような大変な状況のなかで、互いに頑張りましょう、それを認め合いましょうというメッセージが込められています。
F.I.N.編集部
自分で自分を褒めるというニュアンスも入っていますか?
青木さん
入っています。この「自分を褒める」が広く認知されたのが、1996年のアトランタオリンピックでした。女子マラソンに出場した有森裕子さんが、銅メダルを取った時に「自分で自分を褒めたい」とおっしゃったことがきっかけです。これに多くの人が心を動かされました。
当時の有森さんはアスリートとしてさまざまな困難を抱えていました。前回のオリンピックより順位を落としたけれど、それでもなんとか銅メダルに到達できた。「褒めたい」という言葉には、すごく大変なことを乗り越えたんだという背景がきちんとあるんですね。
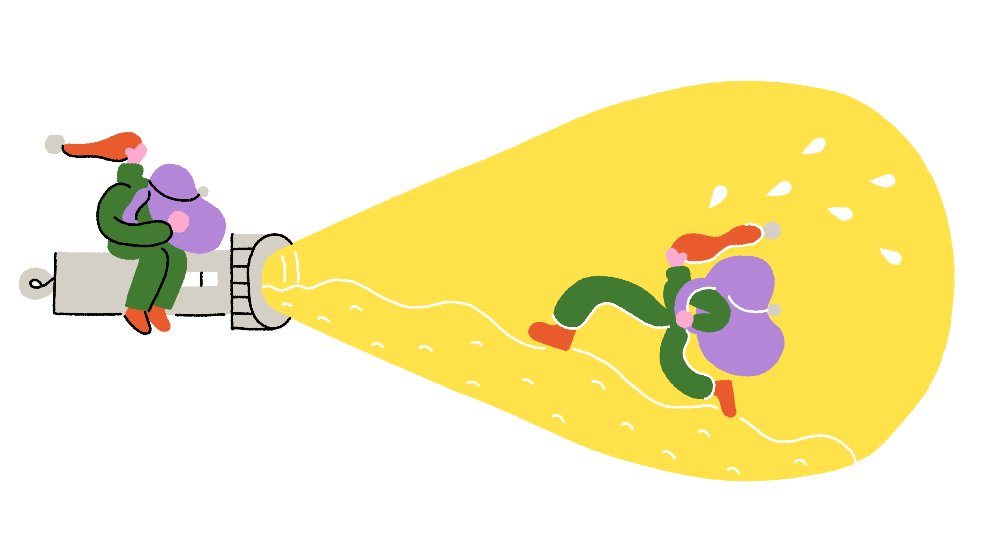
F.I.N.編集部
大変な状況の時に「褒める」広告は出てくるんですね。
青木さん
その通りです。2014年のACジャパンの広告「おとなもほめよう」も、背景としては2011年の東日本大震災の流れがありました。すごく過酷な状況を過ごしてきて、多少落ち着いてきたとはいえ、日本の歴史のなかでも未曾有の経験をしたわけですよね。皆が当たり前に暮らしているわけではなく、過酷なことを経過してきてここまで到達した。そういう時に「褒めよう」という言葉が出てきます。
自信喪失時代のエンパワーメントとしての「褒める」

F.I.N.編集部
2010年代から、「日本すごい」といった、日本を褒めるテレビ番組が増えたような気がします。これにはどんな背景がありますか?
青木さん
これは、これまで説明してきたものとは文脈が違います。自信喪失している人を褒めるというパターン。不安になっていて自分に確信が持てないときに「あなたはそうじゃないよ、大丈夫だよ」と自信を持たせるような、別の種類のエンパワーメントですね。
F.I.N.編集部
不安や自信喪失になったのは、何がきっかけですか?
青木さん
日本は1980年代のバブルの頃から比べると、ずっと下り坂です。失われた30年といわれるほど活気がなく、経済成長も停滞している。大手企業が苦境に立たされるなど、バッドニュースばかりでは日本人が全員、自信を喪失して当たり前です。
そんな時、ますます負のスパイラルに陥らないように、メディア側の人たちが日本のいいところを一生懸命探して番組を作っています。そして視聴者もそういう内容を求めているというインサイトがあるからこそ、番組が続いているのでしょう。癒しだったり、不安や自信喪失に対する一種のエンパワーメントになっているといえます。これは日本が本当に自信を回復するまで続くと思いますよ。
広告がやるべきことは、「優しい消費」を促すエンパワーメント
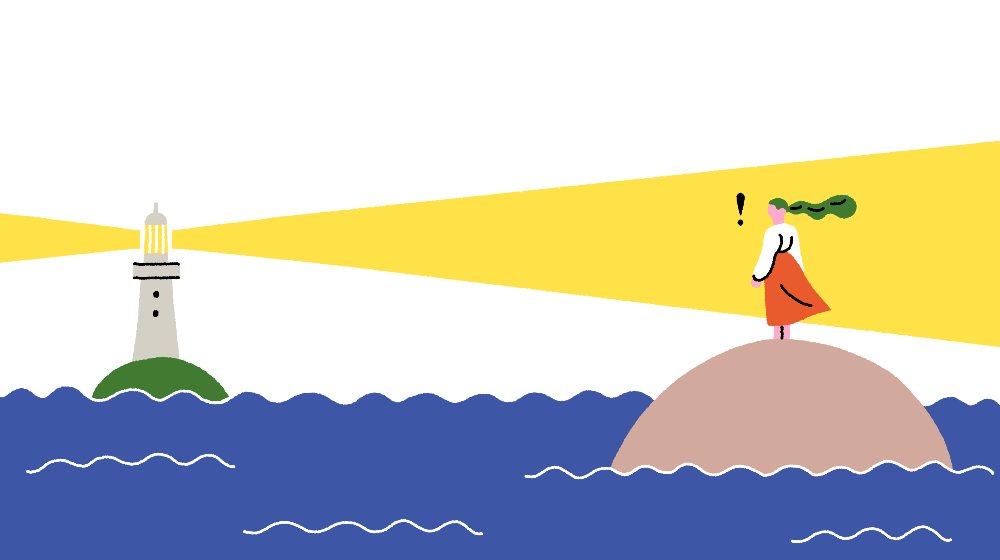
F.I.N.編集部
これから先、人々をエンパワーメントする広告にできることはなんでしょうか?
青木さん
私たちは、過酷な世の中を生きていかなければならない。そのために編み出された生存戦略が「自分で自分を褒めたい」という言葉だったり、デパートの販促などで見かける「自分へのご褒美」だったりするのです。
つまり「消費」というのは、厳しい状況を生き抜くための知恵でもある。広告はずっとその手助けをしてきています。例えば、レディースブランド〈earth music&ecology〉の「ワタシって天才かもねで生きていけ。」(2024)や、ポカリスエットの「自分は、きっと想像以上だ。」(2018)、カロリーメイトの「見せてやれ、底力。」(2016)といったコピーも、ターゲットの自己承認を促進し、自己肯定感を上げるためのエンパワーメントです。
F.I.N.編集部
エンパワーメントこそが、広告に求められる役割なのでしょうか。
青木さん
そう思います。広告表現は、どういうふうに優しいコミュニケーションや優しい消費を盛り立てるかを考えるべきなのではないでしょうか。ご褒美にケーキを食べるのは、ケーキ自体が目的じゃない。「明日から頑張れる自分をつくるため」ですよね。服を買うのも、「自分の審美眼と自分らしさを外へ発信するため」です。広告はその原点に立ち返り、どうすれば消費者を褒め、「自分を奮い立たせるための消費」を提案できるのかを考える必要があるでしょう。
F.I.N.編集部
5年先、10年先の未来、広告はどんなふうにエンパワーメントしていくべきでしょうか?
青木さん
これまでの褒め方は、“今の状態の肯定”といえます。その先にあってほしいのが、これから伸びる可能性を示す褒め方です。景気が停滞したり、消費行動が鈍るのは、人が「このままでいい」と定常状態にとどまってしまうから。だからこそ、広告が果たすべき役割は、その先へ進むための後押しです。「今のあなたでいい。でも、あなたにはもっと多くの可能性がある。その先へ行こうよ」と促していく。そうしたエンパワーメントがこれからますます重要になると思います。人が新しいことに挑戦し、レベルアップした自分を肯定できるようになれば、自然と経済活動も広がっていくはずです。
【編集後記】
青木さんにお話しいただいた「エンパワーメント」という言葉を通して、「褒めること、褒められること」と「優しい消費の提案」はどこか似ていると感じるようになりました。 どちらも勇気づけや認め合いといった側面があり、その先に優しさや幸せがあり、生きるための推進力となるものなのではないでしょうか。
少し大げさな言い方ですが、欲しいものを買う時も、何かを褒める時も、私たちは少なからず幸せについて考え、自分にまつわるものごとを肯定しようとしているのかもしれません。この気づきを忘れないようにしたいと思います。
(未来定番研究所 渡邉)